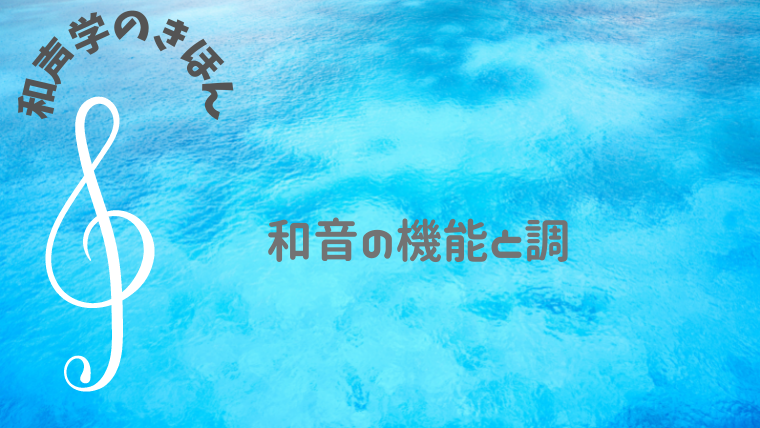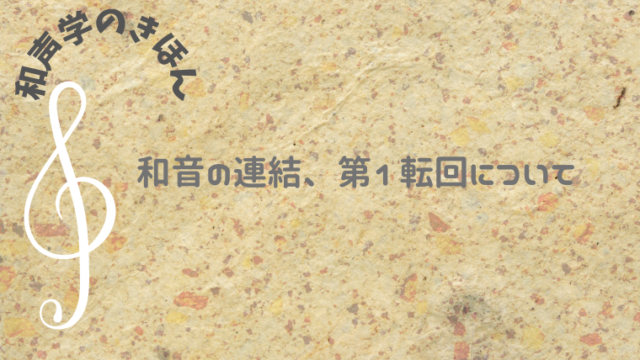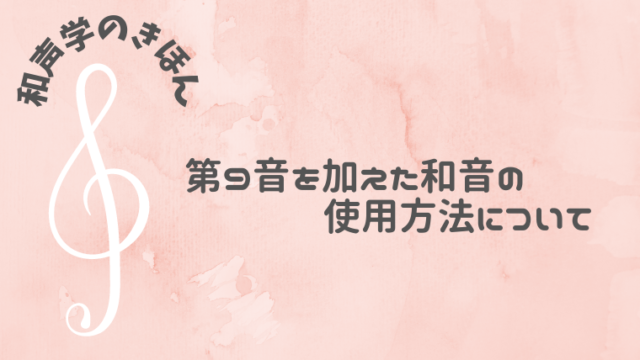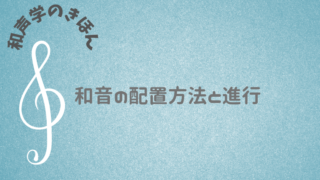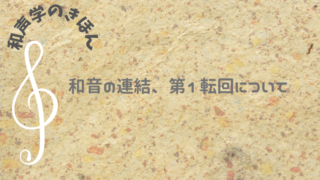こんにちは。当ブログにお越し下さいましてありがとうございます。
このページでは、和音の機能、各種調について紹介したいと思います。
復習をした方は、こちらをご覧ください。
和音の機能
各和音の働き
和音に機能なんてあるの?と思われる方もいらっしゃると思います。
例えば、皆さんが文章を組み立てる時に、主語、修飾語、術後等を組み合わせて作成しますよね。
実は和音も似たような機能で一つの流れを組み立てているのです。
和音の働きには「トニック」「ドミナント」「サブドミナント」の3つがあります。
私の勝手な感覚ですが、「トニック」は言葉でいう主語、「ドミナント」は述語、
「サブドミナント」は修飾語?のようなイメージなのです。
一回目で紹介した音階の各音度の3和音は覚えていますか?
覚えていない方はこちら→はじめての和声~音度と和音の基本
Ⅰ~Ⅶの7種類の和音がありましたね。その和音は、「トニック」「ドミナント」「サブドミナント」
(実習ではトニックはT、ドミナントはD、サブドミナントはSと略記)
のいずれかに分類されます。
トニック(T) →I Ⅵ
ドミナント(D)→Ⅴ
サブドミナント(S)→Ⅱ Ⅳ
※ⅢとⅦは和声学の中では少し特殊なので、別の機会にご紹介します。
C dur(ハ長調)で説明しますと、
トニックはCメジャー、Aマイナー
ドミナントはGメジャー
サブドミナントはDマイナー、Fメジャー
の和音になります。
カデンツの型
カデンツの型は、3種類あります。
- T→D→T
- T→S→D→T
- T→S→T
文章の組み立ても似たようなものがありますよね。
文は主語、修飾語、述語 で表現するように、和音の結合にも似たようなところがあります。
この3種のカデンツが何個もくっついて曲になっているのです。
①は、Tの部分はⅠの和音とⅥの和音を使うことができますが、ⅠとⅥを続けて使う場合は、必ずⅠの後にⅥを配置します。
②は、イメージはハノンのスケール最後のカデンツですね。
SにはⅡの和音とⅣの和音が使用できますが、ⅡとⅣを続けて使う場合は、必ずⅣの後にⅡを配置します。
③は、あまり頻繁には使いませんが、よく曲の最後に使用したりします。
最初のTにはⅠまたはⅥが使用できます。SはⅣしか使用できません。そして、最後のTはⅠのみの配置となります。
①~③すべての項において、ドミナントはVの和音のみの使用となります。
各和音の進行先
ⅠはⅡ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ と一番多くの和音に行ける和音となります。言語でいう主語的なものでしょうか。
ⅡはⅤにしか行けませんが、サブドミナントとしてⅣより好んで使います。
ⅣはⅠとⅡとⅤに行けます。実習の中ではⅡとⅤに行くことが多いです。
ⅤはⅠとⅥ(トニック)にしか行けません。言語でいう述語みたいな感じでしょうか。
ⅥはⅡとⅣとⅤに行けます。トニックなのでIと似たような使い方ができますが、長調ではⅠはメジャーコードでⅥはマイナーコードになります。(短調だとその逆。)
今紹介したように、和声学は和音の進行先に制限があります。
ポピュラー音楽を聴いていると、だいたいは似通った進行(T→S→D→T)をしてはいるのですが、
特に進行先の制限はないですよね。ドミナント属性コードの後にサブドミナント属性コードが
来たりとかも見かけます。
どっちが悪いということでなく、和声学を学習していると、身の回りで流れてくる
Popsのコード進行も手にとるようにわかるようになりますし、色々なコード進行に
敏感になります(笑)
調
今までの説明の中で時々dur(長調)、moll(短調)という言葉がでてきたと思いますが、
これは詳しく説明しなくてもご存知の方は多いかもしれません。
和声学では色々な長調、単調での実習があります。
調は長調、単調12種ずつ計24種類あり、すべての調とその調号がすぐにイメージできるように
しておくのが理想的ですが、多いもので6つの調号がつくので、苦手な方も多いでしょう。
(自分も調号6つは苦手です汗)
実習しながら、調も少しずつ覚えていきましょう。
様々な調ですぐに各音度の和音が認識できることは実習の助けになります。
もうひとつ、短調の音階は調号とは別に第7音が半音上がります。
そのため、短調の課題を解く際は、長調より増音程進行をやってしまいがちですので
その点にも気を付けましょう。
まとめ
以上、主に和音の機能や進行・調について紹介しました。
だいぶ説明だらけになってしまいましたが、(いつも?)
前回に続き、しっかり積み重ねていきましょう。
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。